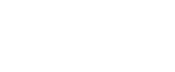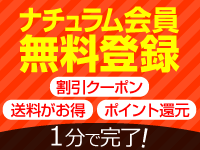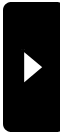2018年03月13日
桃色の歯茎と白い前
わからないことがある——。僕は買い食いのクセがついた。学校からの帰りみち、僕は菓子屋へよって甘ナットウを買った。なぜそんなことをするのか。子供のころから僕は甘い菓子がきらいだった。好きなのはウデ玉子とバナナだ。ウデ玉子は弘前《ひろさき》から東京へ引っ越したとき汽車の中で弁当のかわりに十七個食べた記録がある。バナナは小学六年のとき、いっぺんに十三本食ったのが最高だ。一人ッ子の僕には、きめられたオヤツなどはなかったし、母は「好きなものなら、いくら食べさせても大丈夫」という主義だった。事実、嫌いなものでなければ僕は、どんなにたくさん食べても、吐いたり、腹を下したりはしたことがない。寺へ来てからは、出入りの棟梁《とうりよう》や植木の職人などと同じように、僕はオヤツをあたえられる。学校からかえると、女中の勝ちゃんが台所の煉炭火鉢で、六つに切った松の葉の焼き形のついたマンジュウをあぶっている。はじめのうち僕は、それが仏壇の上にあがっている葬式マンジュウだとは知らなかった。ただ毎日きまって同じものを出されると、切り口のアンが白く乾いたのを見ただけで、もう口の中じゅう煉炭のキナ臭いにおいでいっぱいになりそうな気がする。
「たまには甘ナットウか、水ようかんでも食べてみたくなるわね」
奥さんの眼を盗んで勝子は、焦げ目のついたアンコをまずそうに食いちぎりながら言った。
「うん……」
水ようかんも甘ナットウも、たいしてうまいとは思っていない僕は、あいまいにこたえた。すると勝子も、煉炭火鉢のまえで立て膝した脚を崩しながら、僕の方を向いてあいまいに笑った。桃色の歯茎と白い前歯のすきまにアンコの黒いつぶが覗いてみえる。唾《つば》にぬれて黒く光っているアンコの小さなかたまりが不意に、僕にあることを連想させた。——あれを舐《な》めたら、きっと甘いだろう、僕は心の中でツブやいた。けれどもそれは葬式マンジュウのアンとはちがった種類の甘さにちがいない——。
もっとも僕は菓子屋の店先きで別段、そんなことを憶い出したりしてはいなかった。とおりがかりに、ガラスの壺の中で白い粉をふいている甘ナットウを見かけると、何となく店の中へ入ってしまったのだ。黒いの、白いの、アズキ色の、茶の、みどりの、と甘ナットウにも、いろんな種類があるものだということを、その時はじめて知った。僕は一番ありふれたアズキ色のを買った。店を出ると、急に僕はバクダンでもかかえこんでいる気になった。親に黙って物を買ったという経験は、これが最初というわけではない。思いついたものを途中で買って、あとでそれを母に話す。家にいるときなら、それでよかったわけだ。しかし、いまはそうは行かない。こっそり買った菓子を、先生や奥さんに見つけられては具合が悪い気がする。みちみち僕は追われる気持で紙袋から甘ナットウを頬ばった。——どんな味がしただろう? うまいとは思わなかった。といって、まずくもなかった。ただ口の中が重苦しく甘ったるいものでいっぱいになるたびに、僕は沸き立つ欲望に胸を突き上げられ、怖さといっしょにそれを呑《の》み下した。とうとう寺にかえりつくまでに大半たいらげて、紙袋の底の方にいくつか残ったやつを、あとで勝ちゃんにやった。「ありがとう」と彼女は袋の中をのぞきこみ、「あら、これはウズラじゃないの、本当においしいのはソラマメなのよ」と言った。すると僕は、なぜかこの女にダマサれたような気がした。
それ以来、僕は毎日、菓子屋へよるようになった。勝子に言われたソラマメの砂糖漬《さとうづけ》も買った。なるほどそれは、うまいといえばうまいようだった。要するに、だんだん食い物の味がしてきた。もう勝子に残してきてやったりはしなかった。かくれてものを食うことが平気になったからだ。夜、寝床にもぐって甘いものを食うことは、僕に赤ん坊のころを夢みさせる。何も見えない真暗なところで生温いものに包まれながら、お乳を吸った記憶は、きっとまだ体の中のどこかに残っているにちがいない。口の中の舌や上アゴが甘いにちゃにちゃしたもので溶けてくっつきそうになると、頭のシンがどんより重くなり、汗ばんだ手や脚がぐにゃぐにゃしてくる。体全体が熱っぽく、閉じた眼蓋《まぶた》の向う側に、灰色をした波のような帆のようなものが浮んで、ゆっくりとうねりながら近づいては消える。突然、胸苦しさがやってくる。とおくで灰色にうねっていたものが、ヒダヒダのいくつもある洞穴《ほらあな》の壁に見え、僕は底の方へ体ごと吸いこまれる。桃色をした歯のない歯茎が、ぽっかり黒い口をあけて眼の前にせまり、僕は身動きもならず、その口の中へ呑みこまれる。声もたてられない怖ろしさで、胸のドキドキするのが体じゅうに反響する。……耳の穴の奥の方で、バリバリと叩きつける雨のような、滝のような音が聞えて、眼がさめる。
あれは勝子のしょうべんの音だ。その音で僕は何の